■政治家--新釈国語 ― 2009/07/01
国の内外に揉め事や争い事などが起きないよう予め実情を調べて対策を立て、それらを法案として議会に提案して国民の合意を取り付けることに日夜勤(いそ)しむ人々。現職の国会議員またはその経験者について用いることが多く、これを地方議会議員に用いるときはやや異なった意味合いが含まれる。同じような活動を行っていてもその目的が私利私欲と保身に傾きがちな人々、駆け引きや根回しが巧くても党利党略を優先する人々と真の意味の政治家とは区別されなければならないが、日本では基準となるべき政治責任の中身が曖昧模糊としているため専らマスコミ報道に頼ってこの判断を下そうとする嫌いがある。なお公的な責任感に欠け、自己と特定地域・団体の利益のみを追求する議員は軽蔑して「政治屋」と呼ばれるが、これと英語の politician とは全く異なるものである。米語の場合は多分に共通する意味合いを含むとは言え、政治風土を無視して単純に同一視するのは妥当な解釈とは言い難い。
■人を見る目--新釈国語 ― 2009/07/01
警察官、検察官、裁判官にとりわけ求められる力のひとつ。これらの職業に就く者にこの力が欠けると冤罪を生む可能性が高くなり、罪なき者を苦しめるだけでなく結果として犯罪者を蔓延(はびこ)らせることにもつながる。また企業の人事担当者にこの力を欠く場合は優れた人材の確保が難しく、幹部社員にこの力を欠く場合はせっかく採用した人材を失うことにもなりかねず、いずれの場合も結果として企業の存続を危うくする。
政治家の場合も同様で、党首に相応しい人を選ぶための見る目がないと、選挙のたびに議席を失うのではないかとびくびくさせられる。国民の場合は議会に送る人を選ぶ目を持たないと、無策の付けを背負わされ増税に喘ぐことになる。
政治家の場合も同様で、党首に相応しい人を選ぶための見る目がないと、選挙のたびに議席を失うのではないかとびくびくさせられる。国民の場合は議会に送る人を選ぶ目を持たないと、無策の付けを背負わされ増税に喘ぐことになる。
○かぼちゃ(1)--夏野菜 ― 2009/07/01
極東という呼称の由来を聞き、そう呼ばれる地域が地球上のどこにあるかを知れば、西瓜も南瓜も実に有意味な名称だと思うだろう。そして東瓜や北瓜が存在しないことも大方は想像が付くだろう。極東の東にはもう太平洋しかないし、北にはシベリアや千島列島など極寒の地しかない。植物の渡来があるとすれば、どう考えてもそれは西か、または南からということになる。実際ふたつとも、そうした歴史を背負った名称を付けられたのである。
面白いのは西瓜が文字も発音も中国からの借り物であるのに対し、そう違わない時期に渡来したと思われる南瓜の方は何故か「ナンカ」ではなく「かぼちゃ」の方が普及したことである。いま日本語の中で語尾が「ちゃ」で終わる言葉と言えば、お茶に由来するものか、あとは「むちゃ」「くちゃ」「めちゃ」の類であろう。この呼称の源が「カンボジア」にあることは疑いないとしても、当時の人々の耳に聞こえたであろう音は「カムボヂャ」であり、やがて「ム」が抜け落ちて「カボヂャ」となり、さらに「ヂャ」が清音化して現在の「かぼちゃ」が出来上がったことになる。せいぜい400年かそこら昔の話だろうが、おおもとの選択理由が気になる。
面白いのは西瓜が文字も発音も中国からの借り物であるのに対し、そう違わない時期に渡来したと思われる南瓜の方は何故か「ナンカ」ではなく「かぼちゃ」の方が普及したことである。いま日本語の中で語尾が「ちゃ」で終わる言葉と言えば、お茶に由来するものか、あとは「むちゃ」「くちゃ」「めちゃ」の類であろう。この呼称の源が「カンボジア」にあることは疑いないとしても、当時の人々の耳に聞こえたであろう音は「カムボヂャ」であり、やがて「ム」が抜け落ちて「カボヂャ」となり、さらに「ヂャ」が清音化して現在の「かぼちゃ」が出来上がったことになる。せいぜい400年かそこら昔の話だろうが、おおもとの選択理由が気になる。
■グリーンダム--新釈カタカナ語 ― 2009/07/02
グリーンダム・ユース・エスコートの略。中国政府がインターネット上の猥褻なコンテンツから青少年を保護するためとして巨費を投じて開発したインターネット規制ソフトのこと。当初の予定では今年7月1日から中国国内で販売するパソコンは全てこのソフトをインストールした上で出荷しなければならないと命じていたが前日の6月30日になって急遽、実施延期が発表された。延期の理由やいつまで延期するかなどは明らかにされていない。このソフトについては性的な有害情報だけでなく、天安門事件やチベット問題など反体制・独立運動に関係するページも一律にブロックされて閲覧できなくなることが分かり、中国国内および欧米各国から猥褻なコンテンツの規制を口実にした思想・情報統制ではないかと反発や批判の声が挙がっていた。
■使い捨て(2)--新釈国語 ― 2009/07/02
この語は人間に関しても用いられるようになった。この場合も、その実態は大きくふたつに分かれる。ひとつは企業が若く元気な社員や仕事のできる社員を目一杯働かせるだけ働かせ、健康を損ねたり草臥(くたび)れてあまり働けなくなったと判断すると今度はあの手この手を使って退職を余儀なくさせるといった人事労務政策をいう。不動産販売などの営業マンや漫画雑誌などの編集者にしばしば見られる例である。
もうひとつは近年、顕著になった政界における使い捨ての例である。政権与党の代表者選びに際し候補者の実績や政治的手腕よりも国民に受けが良いか・人気が出そうかというタレント並みの基準が適用されるため、マスコミが創り上げた虚像に加勢され圧倒的な支持を集めて就任する者を多く見受けるが、やがて予想が外れたと分かると躊躇(ためら)うことなく梯子を外して次の候補者探しに駆け回ることを指す。
選ばれた代表者も己の実力の程度に気づけばさっさと辞めるし、気づかない場合でも睡眠不足に悩まされたり体調不良を感じれば辞めざるを得なくなるが、中には非力無勢を忘れていつまでもぐずぐずと職に留まる者もいるため、2階から引きずり下ろされたり後ろから伏兵に突き落とされて怪我をするのではないかと案じられることもある。(了)
⇒http://atsso.asablo.jp/blog/2009/06/24/ 使い捨て(1)
もうひとつは近年、顕著になった政界における使い捨ての例である。政権与党の代表者選びに際し候補者の実績や政治的手腕よりも国民に受けが良いか・人気が出そうかというタレント並みの基準が適用されるため、マスコミが創り上げた虚像に加勢され圧倒的な支持を集めて就任する者を多く見受けるが、やがて予想が外れたと分かると躊躇(ためら)うことなく梯子を外して次の候補者探しに駆け回ることを指す。
選ばれた代表者も己の実力の程度に気づけばさっさと辞めるし、気づかない場合でも睡眠不足に悩まされたり体調不良を感じれば辞めざるを得なくなるが、中には非力無勢を忘れていつまでもぐずぐずと職に留まる者もいるため、2階から引きずり下ろされたり後ろから伏兵に突き落とされて怪我をするのではないかと案じられることもある。(了)
⇒http://atsso.asablo.jp/blog/2009/06/24/ 使い捨て(1)
○かぼちゃ(2)--夏野菜 ― 2009/07/02
生ゴミはなるべく出さないように気を付けていても、畑で落とし損ねた黄色の葉っぱが見つかることもあれば、ゴボウの皮のように時には捨てざるを得ないこともある。南瓜の種もそうしたもののひとつである。子どもの頃はおやつ替わりによく食べたが近頃は滅多に口にしない。そのため生ゴミに混じってコンポストへ押し込められる。コンポストが満杯になると、出来上がった堆肥の一部として底の方から取り出され畑に撒かれる。このとき南瓜の種はまだ生きている。
生きているから、時期が来ると、畑のあちこちで雨後の竹の子のように芽を出す。南瓜ばかり作るわけではないから、多くはいつか抜かれてしまう。だが運良く畑の隅などに芽を出したものはそのまま放置される。こうして南瓜は毎年、誰意識することなく栽培され、蜂の活躍などでうまく受粉できた雌花には可愛い南瓜の子が育ち始める。一方、雌花ではあっても雄花から花粉を届けてもらえなければ、やがて黄色に変色し腐ってしまう。
南瓜には雄花がひょろひょろといっぱい付く。昨日の写真には開花前の雄花が2本写っている。今日の写真は雌花である。花がややしぼみかけ、受粉期が終わったことを示している。花の下にある小さな赤ちゃんが育つかどうかは、あと四五日もすれば分かるだろう。急に成長が始まれば、初秋には実りが期待できる。西瓜も南瓜も秋の季語だが、花は夏の季語である。(つづく)
上空をB29が飛ぶ南瓜花 関淡水
生きているから、時期が来ると、畑のあちこちで雨後の竹の子のように芽を出す。南瓜ばかり作るわけではないから、多くはいつか抜かれてしまう。だが運良く畑の隅などに芽を出したものはそのまま放置される。こうして南瓜は毎年、誰意識することなく栽培され、蜂の活躍などでうまく受粉できた雌花には可愛い南瓜の子が育ち始める。一方、雌花ではあっても雄花から花粉を届けてもらえなければ、やがて黄色に変色し腐ってしまう。
南瓜には雄花がひょろひょろといっぱい付く。昨日の写真には開花前の雄花が2本写っている。今日の写真は雌花である。花がややしぼみかけ、受粉期が終わったことを示している。花の下にある小さな赤ちゃんが育つかどうかは、あと四五日もすれば分かるだろう。急に成長が始まれば、初秋には実りが期待できる。西瓜も南瓜も秋の季語だが、花は夏の季語である。(つづく)
上空をB29が飛ぶ南瓜花 関淡水
●部首の話(予告) ― 2009/07/02

明日から、漢字を構成する重要な要素である「部首」について短文の解説記事を掲載します。康煕帝(コウキテイ)は中国清代の第4代皇帝ですが、武勇だけでなく学術の振興奨励でも知られる人です。その勅命により編纂された「康煕字典」12集42巻は従来の字書の集大成として4万7千を超える漢字を214の部首に分類して部首の画数順に並べ、同部首内はさらに画数順に排列しました。これが今日、多くの字書に見る漢字の整理方式です。
最近は漢字に対する関心が高まっているとも聞きますが、学生などを見ていると部首については案外知らないように感じます。民族の知恵ともいうべき漢字の文化に、文字成立の視点から触れていただくことが狙いです。掲載は毎週金曜日です。
最近は漢字に対する関心が高まっているとも聞きますが、学生などを見ていると部首については案外知らないように感じます。民族の知恵ともいうべき漢字の文化に、文字成立の視点から触れていただくことが狙いです。掲載は毎週金曜日です。
○かぼちゃ(3)--夏野菜 ― 2009/07/03
茨城県南部の江戸崎町(現・稲敷市江戸崎)は知る人ぞ知る「えびすかぼちゃ」の産地です。40年ほど前に高野平さん達7人のお百姓さんが始めた努力が実って、今ではグルメ向きのお中元にも利用される高級ブランドとなっています。栽培農家の数も6倍近くに増えたそうです。美味しい南瓜づくりのコツは何といっても良質の堆肥をふんだんに使った土つくりにあります。実際に自分で栽培してみると、それがよく分かります。そして畑にぎりぎりまでおいて完熟させることです。
美味しい南瓜は蔓の太さも茎の太さも肉の厚さも、輸入物や他の産地のものとは比較になりません。ずば抜けています。身の堅さは並の包丁を寄せ付けません。爪を立ててもなかなか傷が付きません。ようやく包丁が通ると、黒に近い濃緑の皮の下から山吹色か黄金色かと思うような見事な肉厚の身が顔を出します。煮ても揚げても、裏ごししてサラダにしても美味しい南瓜ですが、「江戸崎かぼちゃ」ならではの通の調理法を先ほどの高野さんから教わってください。次の頁で、高野さんの優しそうなお顔と一緒にご覧になれるはずです。(つづく)
⇒http://www.ib.zennoh.or.jp/santi/h03.html ほれぼれ産地便り(JA稲敷)
美味しい南瓜は蔓の太さも茎の太さも肉の厚さも、輸入物や他の産地のものとは比較になりません。ずば抜けています。身の堅さは並の包丁を寄せ付けません。爪を立ててもなかなか傷が付きません。ようやく包丁が通ると、黒に近い濃緑の皮の下から山吹色か黄金色かと思うような見事な肉厚の身が顔を出します。煮ても揚げても、裏ごししてサラダにしても美味しい南瓜ですが、「江戸崎かぼちゃ」ならではの通の調理法を先ほどの高野さんから教わってください。次の頁で、高野さんの優しそうなお顔と一緒にご覧になれるはずです。(つづく)
⇒http://www.ib.zennoh.or.jp/santi/h03.html ほれぼれ産地便り(JA稲敷)
■求心力--新釈国語 ― 2009/07/03
ある目的のために政治運動や社会運動などを行う団体において、そこに結集した者同士が目的達成のために団結し、代表など組織運営の中心となる人の下にまとまろうとする力のこと。政党のような互いに何らかの主義や主張が共通する者同士が寄り集まって結成する団体であっても、これを単なる仲良しクラブで終わらせないためには、組織としての最低限の約束事や決まり事が必要である。それがないと細部で意見が分かれたり利害の対立があるたびに烏合の衆となって組織は瓦解し、結党の目的を果たすことができない。党内の意見をうまくまとめて利害を調整し、参加する者が一丸となって目的達成に向かえるよう努めるのが党首や代表の役割であるとするなら、求心力は党首や代表を裏で支える力だとも言える。
この力は政党活動を円運動にたとえることで、力学的に説明することも可能である。物体の運動に関する基本的な法則は発見者の名前を採って「ニュートンの法則」と呼ばれるが、第1法則は有名な「力を受けない物体は静止または等速直線運動を続ける」である。つまり運動している物体は、そこに何らかの力が働かない限り真っ直ぐに進むことになる。だから等速ではあっても円運動している物体には何らかの力が加わっていると見なければ、円運動の説明は成り立たない。そこで考え出されたのが速度に対して垂直(つまり中心方向)に向かう力の存在である。力学では円運動の中心方向に向かうこの力は、向心力と呼ばれる。
政党活動における求心力は自然界における向心力とよく似た働きをしている。円運動の中心には党首や代表がいて、その周囲で活動する党員には力学でいう向心力が常に働いていなければならない。この力が薄れたり弱まったりすると運動を続ける党員達の行動はたちまち円運動から直線運動へと変じ、組織としてのまとまりは崩れることになる。人間界では、党首や代表を中心にまとまろうとするこの力を人間くささを感じさせる求心力などと称しているが、力学的な力の関係で見れば物体の運動と大差ないことに気づく。
この力は政党活動を円運動にたとえることで、力学的に説明することも可能である。物体の運動に関する基本的な法則は発見者の名前を採って「ニュートンの法則」と呼ばれるが、第1法則は有名な「力を受けない物体は静止または等速直線運動を続ける」である。つまり運動している物体は、そこに何らかの力が働かない限り真っ直ぐに進むことになる。だから等速ではあっても円運動している物体には何らかの力が加わっていると見なければ、円運動の説明は成り立たない。そこで考え出されたのが速度に対して垂直(つまり中心方向)に向かう力の存在である。力学では円運動の中心方向に向かうこの力は、向心力と呼ばれる。
政党活動における求心力は自然界における向心力とよく似た働きをしている。円運動の中心には党首や代表がいて、その周囲で活動する党員には力学でいう向心力が常に働いていなければならない。この力が薄れたり弱まったりすると運動を続ける党員達の行動はたちまち円運動から直線運動へと変じ、組織としてのまとまりは崩れることになる。人間界では、党首や代表を中心にまとまろうとするこの力を人間くささを感じさせる求心力などと称しているが、力学的な力の関係で見れば物体の運動と大差ないことに気づく。
●聿部(ふでづくり・6画) ― 2009/07/04
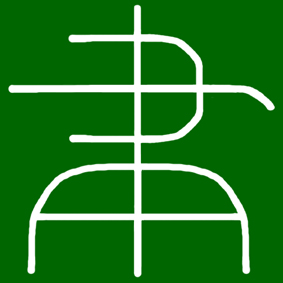
聿が部首であることを知る人は多くない。確かに筆にも律にも建にも津にも聿は構成要素として登場する。だが筆は竹冠(たけかんむり)、津は三水(さんずい)、律は行人偏(ぎょうにんべん)、建は廴繞(いんにょう)のはずである。これらが急に聿部に配置替えになることは考えにくい。
実は聿を部首とする漢字はいくつもない。しかし覚えて欲しい字がある。厳粛とか粛々と言うときの粛である。今は部首内5画の略字を使うが、正字は部首内7画の肅である。他にも人名によく使われる肇がある。「貧乏物語」で知られるマルクス主義経済学者の河上肇はこの字を使う。そして読書家であれば知って欲しいのが肆である。店の意であり、書肆は書店、酒肆は酒屋である。
ところで聿は単独でも使用され「イツ」という漢音をもっている。図示したのは現在の「ふで」が出来上がるより前の、ごく初期の時代の筆記具をかたどったものである。三千年以上前の殷の時代には既に毛筆の「ふで」が存在したというから、時代はさらに遡ることになる。この時代の主な役割は甲骨に吉凶を占うための卜辞と呼ばれる文章を刻みつけることだった。全くの想像だが原形は木片に近く、先は細く削られていて割れ目があり、そこに墨を染みこませることで筆記を可能にしたのではないだろうか。
やがて細い竹の一方の端を叩いて細かく砕き、後に穂と呼ばれる部分の原形が発明される。これが竹筆である。そしてこの部分にもウサギ、ヒツジ、イヌ、ウマ、タヌキ、キツネ、シカなどの毛を用いる工夫が始まり、現代の「ふで」により近いものへと改良されてゆく。この過程で聿は廃れ、筆が取って代わるようになった。聿が筆記具として珍重された時代は今となってみればそう長くは続かなかった。だから「康煕字典」が編纂された清代には聿の字の使用頻度は低く、かろうじて部首には残ったものの、そこに筆や律の姿を見ることはなかったのである。
なお他の部首に属する漢字に聿が用いられている場合、それらの全てが聿に該当し「ふで」の意を含んでいるかは精査してみないと分からない。例えば津の場合は聿ではなく専ら進の篆書体とする説が知られている。
実は聿を部首とする漢字はいくつもない。しかし覚えて欲しい字がある。厳粛とか粛々と言うときの粛である。今は部首内5画の略字を使うが、正字は部首内7画の肅である。他にも人名によく使われる肇がある。「貧乏物語」で知られるマルクス主義経済学者の河上肇はこの字を使う。そして読書家であれば知って欲しいのが肆である。店の意であり、書肆は書店、酒肆は酒屋である。
ところで聿は単独でも使用され「イツ」という漢音をもっている。図示したのは現在の「ふで」が出来上がるより前の、ごく初期の時代の筆記具をかたどったものである。三千年以上前の殷の時代には既に毛筆の「ふで」が存在したというから、時代はさらに遡ることになる。この時代の主な役割は甲骨に吉凶を占うための卜辞と呼ばれる文章を刻みつけることだった。全くの想像だが原形は木片に近く、先は細く削られていて割れ目があり、そこに墨を染みこませることで筆記を可能にしたのではないだろうか。
やがて細い竹の一方の端を叩いて細かく砕き、後に穂と呼ばれる部分の原形が発明される。これが竹筆である。そしてこの部分にもウサギ、ヒツジ、イヌ、ウマ、タヌキ、キツネ、シカなどの毛を用いる工夫が始まり、現代の「ふで」により近いものへと改良されてゆく。この過程で聿は廃れ、筆が取って代わるようになった。聿が筆記具として珍重された時代は今となってみればそう長くは続かなかった。だから「康煕字典」が編纂された清代には聿の字の使用頻度は低く、かろうじて部首には残ったものの、そこに筆や律の姿を見ることはなかったのである。
なお他の部首に属する漢字に聿が用いられている場合、それらの全てが聿に該当し「ふで」の意を含んでいるかは精査してみないと分からない。例えば津の場合は聿ではなく専ら進の篆書体とする説が知られている。



最近のコメント